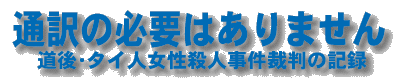
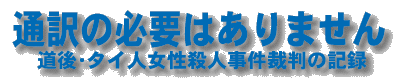
|
1998年3月、高松高裁で判決が下りた後、私は16年間住んだ松山を離れて、栃木県宇都宮市に移り住んだ。オンが栃木刑務所に収監されていることがわかったのは、その後だ。栃木刑務所は宇都宮から車で一時間の距離にある。面会ができるわけではないが、彼女が近くにいることに、何となくほっとした。 今年(98年)10月初め、東京のタイ大使館からアッタカーン領事が栃木刑務所を訪れた。アッタカーン氏は、控訴審の始まる前から事件に関心を寄せてきた人だ。 オンも含めて数十人のタイ人女性服役者に面会した領事の話から、オンが元気でいることはわかった。 北関東の冬は厳しい。この寒い冬を6回越えないと、オンは暖かい故郷に帰ることができない。 この裁判には高松のグループを中心に、たくさんの人々が関わった。公判毎に発行したニュ−スは約200人に送られ、それに応えてカンパを寄せてくれた人も100名を越えた。決して裕福ではない人達からの、決して多くはない支援金だが、裁判を支えたのはそのお金だった。しかし「たったの」100人だ。多くの人の無関心と、冷淡な反応に、声の届かないもどかしさを感じることが多かった。 「普通の日本人」にとっては、タイ人女性の事件など「自分と関係のないこと」にすぎないのだろうか。 私は実はそうは思っていない。多くの日本人がオンの事件に触れたくないのは、「自分と関係のないこと」だからではなく、逆に、余りにも「自分に近すぎる」からなのだと気づいたのだ。 距離的にも遠く、間違っても自分が巻き込まれないだろうと思えるものについては、人々は結構関心を寄せるものだ。「誰にでもできる」「小さな善意」等々の言葉に共感を寄せる人は多い。余力をもった関係、とでも言うのか、自分の生活が脅かされない範囲では、人はいくらでもやさしくなれるのだ。 だが、少しでも自分の生活に触れるものに対しては、人は無意識的に反応し、無関心を装って避けるか、冷酷な対応に走る。 特に、かつての日本人社会が予想していなかっただろう滞日外国人の増加について、その反応は顕著だ。 単なる滞在期限切れや資格外就労をしているにすぎない外国人に対して、「不法外国人」なる悪意のこもった言葉を使う国では、オンの言葉など人々に届くはずもない。 日本人の多くは、実はオンたちのような、買春の相手に供せられた外国人女性を具体的に知っている。 彼女たちを性の道具として買ったことがある男、そうした買春者を夫や恋人にしている女、彼女たちが生活している場を知っている人は、けっこうな数になるはずだ。 オンを知っている男はたくさんいる。だが、その中の一人として彼女のその後に関心を持つ者はいない。買春者は、女に出会いや関係も求めているわけではないからだ。 性を人そのものと切り離した買春は、女を徹底してモノ化することでしか存在しえない。 モノ化された女への視線がどんなものか、この裁判は実にはっきりと示してくれた。 売られ、買われた女の状況に、少しの想像力も持ちえない裁判関係者もまた、買春者の感覚を持つものだ。 日本の男たち、そして彼らと共にいる私たちの、それぞれの性の有り様を考える事なしに、この事件を語ることも、忘れることもできない。 出会いに感謝、というにはあまりに後味の悪すぎる出会いだった。 私は決して忘れない、そして決してこのままにはしない、オンも私たちもみんな等しく幸福になる権利を持った女だ、ということをオンに伝えたいと思う。 1998年12月27日(道後事件から9年めの日) 深見 史 |